こんにちは。ムッタ先生です。
今日は、今話題になっている『自分の親に読んでほしかった本』フィリッパ・ペリー を紹介します。
子育て中の親向けの本のように思われますが、教師にもぜひ読んでもらいたい一冊です!
この本を読むことで、子供との向き合い方や保護者への見方も変わるはずです。
内容と印象深かったエピソードを紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください!
『自分の親に読んでほしかった本』について
著者について
フィリッパ・ペリー(Philippa Perry)は、イギリスの著述家、心理療法士、テレビのパーソナリティとして知られています。
彼女は特に心理学や人間関係に関するテーマに焦点を当てた著作で多くの読者に支持されています。
『自分の親に読んでほしかった本』はその代表作の一つで、親子関係を深めるための実用的なアドバイスが評価されています。
内容
この本の特徴は、親子関係を「完璧」であることを目指すのではなく、感情的なつながりを深め、健全で柔軟な関係を築くことに焦点を当てている点です。
親としての自分を見つめ直し、子どもとのコミュニケーションや感情的な対応を改善するためのアドバイスが詰まっています。
また、親がどのようにして子どもと健全な関係を築けるか、またはすでに傷ついてしまった関係をどのように癒すかについて語っています。
印象深かったエピソード
子供は親の言うことではなく、親がすることをする
「子は親の鏡」
よく使われる言葉ですよね。
著者は子供の時、お母さんが鏡を見ながら自分の粗探しをしていた姿を見ていたそうです。
自身が母親になって、まったく同じことをした時に、娘から「お母さんのそういう姿は好きじゃない」と言われたそうです。
子供の頃の経験はとても重要で、自然と親の行動が子供に影響を与えてしまっているというのです。それは良い意味でも悪い意味でも。
例えば、挨拶や言葉遣いが丁寧な子供がいた時に、保護者面談でその親も言葉遣いや礼儀作法が丁寧で、「この親あってこの子ありだな」と思ったことがあると思います。
同じように、学校で言葉遣いが悪い子供がいた時には、親や兄や姉が乱暴な言葉を日常的に用いている場合もあります。
そのような見方をすることで、子供の問題だけでなく、その裏にある家庭の問題にも目を向けることができるようになりました。
正しい境界線を引く
本書での境界線とは、他者に超えてほしくない線で、超えられると冷静さを失い、それ以上のストレスに対処できなくなる限界の部分のことを指します。
良好な関係を築くには、相手にきちんと境界線を明示することが重要で、それは子供に対しても同じだと言うのです。
境界線を引く時には、客観的な事実に基づいたものではなく「私」を主語にして境界線を引き、自分がどう感じているかをはっきり伝えることが重要だそうです。
子供は、明確の線を引かれることで、安心感を持ちながら自分の行動をコントロールすることができるそうです。
黄金の3日間という言葉がありますが、この本を読んで、教師と子供の境界線を引く時間なのだと考えました。
子供達は、初めての教師に対して、何は許されて何は許されないのかをじっと観察しています。学級経営が上手な先生は、子供に対して指導する基準がブレていないなと感じます。
境界線を明確に引くことで、子供達はこれはダメだということが明確になるので、安心して生活できるのでしょう。
コミュニケーションは「ギブ・アンド・テイク」
本書では、2人の教師が例で出てきます。
①生徒が何を知っているか察し、相手に考えされることによって興味を持続させ、生徒が理解したのを確認してから次に行く教師
②一方的に生徒に情報を与えるだけの教師
どちらが良い教師と言えるでしょうか?
もちろん、①の教師と答える人がほとんどではないでしょうか。
みなさん、実際はどうですか?
確実な学習の定着を図ってほしい、失敗させないようにしたいという思いから、最初から必要以上に情報を与えてしまっていませんか。
人間関係で1番ストレスがたまるのは、自分が相手になんの影響も与えられない時だそうです。
「するほうとされるほう」のように、一方が「主」でもう一方が「従」になってしまうと、対等なコミュニケーションは成立せず、習慣化してしまうと良好な関係は失われてしまいます。
子供の意見に真摯に耳を傾け、受け止める姿勢を忘れないようにしたいと強く思いました。
最後に
さて、『自分の親に読んで欲しかった本』いかがだったでしょうか。
保護者向けの本ではありますが、私は教師にもぜひ読んでもらいたい本だと感じました。
保護者対応や学級経営、授業改善など様々な視点からこの本を楽しむことができました。
特に、まだ結婚していない若手の教員には、保護者も子育てに悩みながら頑張っているんだという視点も持てるようになると思います。
お時間あればぜひご一読ください。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました!
|
|
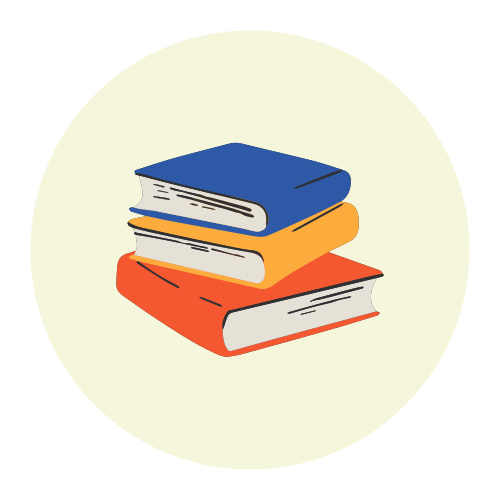

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/407f2796.4987937b.407f2797.56fd959b/?me_id=1285657&item_id=12907969&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01087%2Fbk429611767x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
