こんにちは。ムッタ先生です。
いきなりですが質問です。みなさんは、こんなことを考えたことはありませんか?
「この子のためにもこれは叱らなきゃいけない」
私は、学校教員をしている今でも日々思っていますし、子供たちの成長を思えば正しいことだとずっと思っていました。
数年前から叱らない教育という言葉がテレビなどでも取り上げられましたが、私は正直懐疑的でした。
しかし今回、読んだ本によって、「叱る」という言葉について考えが変わりました。
私が読んだ本は、『「叱れば人は育つ」は幻想』著:村中直人 です。
この本の紹介および印象深かった内容についてお話します。
ぜひ最後までお付き合いください!
『「叱れば人は育つ」は幻想』について
著者
村中直人は、臨床心理士・公認心理師として活動しており、特に発達障害者への支援に力を入れています。
また、教育現場における「叱る依存」の問題についても批判的で、彼の著作には『ニューロダイバーシティの教科書』や『〈叱る依存〉がとまらない』があり、発達障害や社会的な問題に対する深い洞察が含まれています。
内容
本書は、脳・神経科学の観点から「叱る」行為の効果を再考する内容です。
学校、職場、家庭など、様々な場面で行われる叱責が、実際には効果的ではないと述べられています。
叱ることが人を成長させるという信念が「幻想」であると主張し、これに囚われることで人々が無意識に「叱る」行為に依存してしまうことを問題視しています。
また、元麹町中学校長の工藤勇一氏、元女子バレーボール日本代表の大山加奈氏など、複数の識者と対談形式で、「叱る」行為についての議論を深めています。
印象深かったエピソード
「叱る」ことに効果はない
私たちは、どんなときに人を、子供を叱りますか?子供が危ないことをしたとき。友達を傷つけたとき。言われたことをきちんとやらなかったとき。思いつくものはいろいろありますよね。
人が誰かを叱るとき、それは常に相手がよくないことをしたという認識の下に行われます。この状態を何とかして正しい姿、正常な状態にしなくてはいけないという強烈な欲求が湧き上がってきます。
実は、人間には「よくないことをした人を罰したい」という欲求が、脳のメカニズムとして備わっているんだそうです。
そこで叱ったり、罰を与えるなどして、相手にネガティブな感情を与えてコントロールしようとする。これが「叱る」という行動の本質なのです。
学校でも多くの先生が子供を叱っていますよね。
しかし、叱られた子供は多くの場合、強いネガティブ感情を抱いて防御システムが活性化されるそうです。それにより、戦うか逃げるか、どちらかの行動が起こります。先生は権力者なので、逃げることが多くなる。この場合の逃げるとは、物理的に逃げるわけではなく、その場を取り繕うために、「言うことを聞く」「謝罪の言葉を述べる」などの方法で逃げることです。
なんとなく心当たりはありませんか?
叱ることで行動が変わると「ああ、ようやくわかってくれた」「やっと、変わってくれた」と安堵します。そしてこれが、叱る側に「叱ることは有効である」という幻の成功体験を引き起こし、叱る依存になっていくのだそうです。
叱ることの効果はあくまで、現在進行形で行われている危機への介入効果(危険なことをしている人に対してその行為をやめさせる)ことのみです。その後の叱責は単に叱る側の欲求充足に過ぎないそうです。つまり叱ることの効果は「目のの行動を変えさせられる」ということだけなのです。
近年、ベテラン教師の学級崩壊が多くみられるように思います。私も今まで3人ほどそのような先生を見てきました。共通点は、毎日のように子供たちを叱っていることです。なぜ、厳しく叱っているのに学級は崩壊してしまうのか。
その原因がまさに、子供たちをコントロールできているという幻のせいなのだと、この本を読んだことで理解できるようになりました。
自分が強く叱責することで、目の前の人の行動が変わる。それが単なる逃避行動でしかないことを知らなければならないのです。
「叱る」を手放すための「前さばき」
学校ではしばしば「怒るのではなく、冷静に叱るべきだ」という言葉が使われますよね。感情のおもむくままに怒るのはよくない、感情的にならずに冷静に叱るのがよいしかりかただということがよく言われています。
でも、叱られることも怒られることも、受け手にとってネガティブな感情体験となり、心理的圧迫感を受ける状況であることに変わりはないですよね。
「怒る」ことと「叱る」ことは違うんだという論理で叱ることを正当化するのは、叱る側のことしか考えていない身勝手な論理だと筆者は述べています。
だからこそ、叱るを手放すことが必要であり、そこで大事なことが「前さばき」です。「前さばき」とは、叱らないといけないような状況を生み出さないようにするための対処のことです。
多くの場合、「叱る」というのはトラブルが起きてからやることになっていますよね。
事が起きてからではなく、「こういうときにはこういうことが起こりそう」とあらかじめ予測して、事前に注意喚起することで、叱ることを手放すことができますよね。
ただ、それでもできないという場合もあります。「なんでこれだけ言ったのにできないんだ!」と。
そんな時には、不適切な行動が起こる背景には「未学習」か「誤学習」のどちらかの状況があると考えることで、つい叱ってしまう状況も、「これは未学習だからできないのではないか。」とか、「これは誤学習のためにやろうとしないのかもしれない」と考えてサポートできるようになるそうです。
元麹町中学校長の工藤勇一氏は、頭ごなしにこちらの価値観や願望をおしつけて叱るのではなく、問いかけを糸口にして対話をしていく方法として、「三つの言葉かけ」を紹介しています。
①「どうしたの?」②「きみはこれからどうしたいの?」③「先生にできることはある?」
これらの言葉をかけることは、子供が安心して自分の考えを整理するきっかけを作り、信頼関係を築くことにも繋がります。大事なのは、子供たちが自分で考え、自分の行動を変えていくこと。そのために叱るという行為は必要ないのです。
「叱る」ほうがラク
筆者と元日本女子バレーボール代表の大山加奈選手との対談の中で、スポーツと叱ることについての議論が展開されています。私も部活動をやってきた中で、たくさん叱られてきました。
その中で印象的だったのは、大山さんの高校時代のバレー部監督の話です。当時監督だった小川先生は、厳しく叱っているほど指導力があるかのような価値観がまだバレーボール業界全体にあるなかで、選手をまったく怒らず、静かに見守る先生だったそうです。
「こうしろ」という命令的な指示をせず、「どうしたらいいと思うか」という問いかけを使って考えさせるのだそうです。
この話の面白いところは、自分で判断する力を養わせようとする良い先生だと思いますよね。
しかし、高校生の大山選手にとって、どうすれば勝てるかを自分たちで主体性をもって考える、高みを目指すためには何をすればいいのかを考えることがとても大変だったらしく、「先生、怒ってよ、怒って『こうしろ』と言ってくれたほうがラクだよ」と思っていたそうです。
スポーツの世界では特に、こうしろああしろといった指導が「子供たちのためを思って」行われていますよね。しかしこのような指導は、子供たちのスポーツの取り組み方を受動的なものにしてしまう弊害があります。つまり「自分で考えてプレーする力」を奪ってしまうのです。
この問題をややこしくさせているのは、その指導によって、ある程度「勝てる」ことです。しかしその指導が、子供たちが自ら考える力を奪い、受け身であることが「ラク」であると学習させてしまうものだとしたら、それは未来ある子供たちの指導として不適切ですよね。
これは、教師にも言えることではないでしょうか。叱って指導するのはある意味とてもラクなことです。子供たちの行動をすぐにかえることができますから。しかし、子供たちは叱られているうちに、良い悪いの判断を教師に委ねて、自分たちで考える力を失ってしまうように思います。
結果、先生が主張の時などでいなくなると、善悪の判断ができなくなり、ほかの先生から注意されるということがありますよね。これはまさに、子供が考える力を失っているということなのです。
子供たちの未来を考えたときに、「叱る」という行動が適切なのか。すごく考えさせられました。
最後に
みなさん、いかがでしたか。
私自身、これまで多くの子供を叱りながら育ててきました。その当時、それが子供のためになると本気で思って指導していました。そのことへの公開はありません。
しかし、この本を読んで、「叱る」場面に出くわしたときに、「叱らない」という選択肢が増えたように思います。
考え方をガラッと変えるのは難しいと思いますが、少しずつ、「叱る」への向き合い方を変えたいと思える良書でした。
よければ、みなさんも読んでみてください。
それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました!
|
|
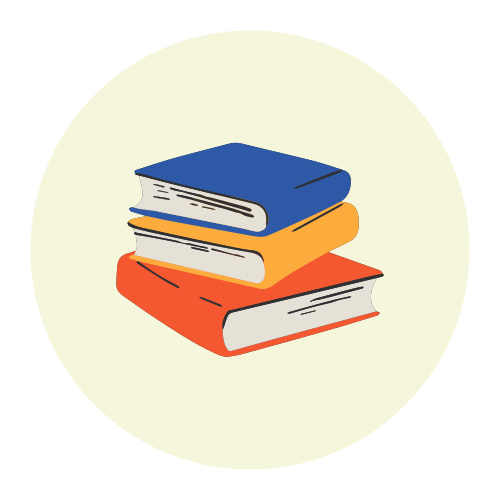

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ffe240e.296cb271.3ffe240f.1c95c8fe/?me_id=1213310&item_id=21319983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3826%2F9784569853826_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す