こんにちは。ムッタ先生です。
先日、私の人生を変えた一冊の本、「教師花伝書」についてお話をさせていただきました。その著者である佐藤学氏が提唱している「学びの共同体」という言葉。みなさんは聞いたことがありますか?
私は、学びの共同体実践をしている学校の授業公開に参加したことがあります。その日のことは、今でも鮮明に覚えています。今日はその日のこと、そして学びの共同体についてお話していきたいと思います。
ぜひ最後までお付き合いください!
衝撃を受けた公開授業
すべてのクラスがグループでの活動
訪れたのは関東のある小学校で、土曜日にもかかわらず多くの教師が参観に来ていました。5時間目はすべてのクラスで公開授業が行われ、6時間目は体育館で算数の授業が公開されました。
最も印象的だったのは、どのクラスも机がコの字型に配置され、子どもたちが顔を合わせながら授業が進行していたことです。
この配置により、教師と子どもだけでなく、自然と子ども同士で意見が交わされ、わからないことがあれば隣の友達に気軽に聴ける雰囲気ができていました。
公開授業後の授業検討会
公開授業の後、その学校の職員全員で授業反省会が開かれました。これまでに私が経験してきた反省会は、主に「ここは改善したほうがいい」といった指摘が中心で、批判的な意見が多く出ていました。
しかし、その学校の反省会では、必ず児童の名前を挙げながら「○○君は先生の問いかけに応じて理解したようでノートを書き始めた」や「○○ちゃんはペア活動で少し戸惑っている様子だったので、もう少し視点を示してあげると良いかもしれない」と、子どもたちの様子を主語にし、教師の発問や手立てについて振り返っていたのです。
頭ごなしに否定するのではなく、子どもにとってより良い授業を作ろうと、みんなで意見を出し合う姿に感動しました。どこか「授業者が批判されて落ち込む」「ベテラン教師が自分の経験を誇示する」ような雰囲気もなく、全員が学びあう姿勢に感銘を受けたのです。
佐藤学先生による講話
実は当初、私は友人と「グループ活動ってどうなの?」とか「教師はこうした方が良いんじゃないか」といった批判的な視点で授業を見ていました。期待していたものと少し違うと感じていたのです。
しかし、その思いを変えたのがその日の最後に行われた佐藤学先生の講話でした。佐藤先生の最初の言葉は、「今日の研修会から何を学び取りましたか。授業を見るとき、あれが良くない、これが良くないという視点ばかりでは教師は成長しません。良いところを見つけて取り入れる姿勢が大切です。」というものでした。
その言葉は、まるで頭を鈍器で殴られたような衝撃でした。佐藤先生の言うように、私は批判ばかりで何も学ぼうとしていなかったことに気づいたのです。
その後、学校で実践されている「学びの共同体」の意図や思いについて説明を受け、授業に込められた真意が理解できるようになりました。もしこの研修に参加していなかったら、今も批判ばかりの教師になっていたかもしれません。
学びの共同体とは
学びの共同体 3つのキーワード
佐藤学氏が提唱している学びの共同体について簡単に紹介していきます。言葉としては難しいかもしれませんが、「学びの共同体」とは、教師、生徒、保護者、地域社会などのさまざまな関係者が協力して、学習プロセスを支援する教育の概念のことだそうです。この共同体では、生徒が能動的に学び、教師が生徒の成長を導き、保護者が家庭での学習を支え、地域社会が学習のリソースを提供することを目指します。
なんだか分かりづらいですね。本を読んでいくと少しずつ理解できてくると思うのですが、興味を持っていただくためにも、よく学びの共同体で出てくる3つのキーワードを紹介します!
- 聴き合う関係:対話を通じて学びを深めるために、互いに意見を聴き合う環境を作ります。
- ジャンプの課題:通常の授業よりも難易度の高い課題を設定し、生徒が挑戦し、協力して解決することで深い学びを促します。
- 真正の学び:教科の本質に沿った学びを重視し、探求的な学習を推進します。
このような取り組みにより、生徒の学力向上や主体的な学びの姿勢が育まれるとされています。
三つの話について簡単に紹介します。
聴き合う関係
聴き合う関係とは何か。それはずばり、わからない子が「どうしたらいいの?」と聴ける関係のことです。
みなさんのクラスでも授業の中で、グループを組んで話し合ったり教え合ったりする時間がありますよね。その時の子供たちの様子はどうでしょう?
佐藤氏は、「話し合い」には学びがないと述べています。なぜかというと、「話し合い」はすでに知っていることの交流ですが、「学び」はまだ知らないことの探究だからだそうです。また「教え合い」もそれ自体が一方的な権力関係となってしまい、できない子は、先生や仲間たちが教えてくれるのを「待つ子供」になってしまうそうです。
私も算数などの学習で、早く終わった子に「ミニ先生ね!」と言って教え合う時間をとっていました。人間は知っているとどうしても教えたくなってしまいます。すぐ算数が苦手な子のところに行き、教えている様子がありましたが、よく見ると一方的に解き方を教えていて、聞いている子は分かったつもりになっているだけ。ということがよくありました。
まさに「待つ子供」を作ってしまっていました。さらに、できる子・できない子という権力関係がはっきりしてしまったのです。
それ以来、ミニ先生の時間を取る際にも、「ここってどうやるの?」と聴かれるまでは教えないというルールを設け、できない子が主体的に聴くことを大切にしました。取り組んでいるうちに、算数が苦手な子も自分から友達に聴けるようになってきました。教えてもらうのは同じかもしれませんが、自分から行動を起こすことに価値があると感じました。
ジャンプの学び
共同的な学びの中では、授業の前半を、その時間で定着を図りたい学習内容などを全体で確認する共有の学びを行います。いわゆるインプットです。
後半では、その学びを生かしてジャンプの課題に挑戦します。つまりアウトプットの時間です。
ジャンプの学びでは、簡単には解けないような問題を設定することで、グループ内の学びにある程度の対等性をもたらされます。学力や知識における差は大きくても、思考し探究する能力の差はそれほどないとこれまでに視察してきた様子からわかっているそうです。
また、ジャンプの学びでは、学力の高い子供は、基礎から発展へ、理解から応用へと考えを広げることができます。一方、学力の低い子供も発展的な学びを通じて基礎を活用することで、基礎的な内容の定着を図ることができるというのです。
例えば、1年生の算数でいえば、共有の学びで1けたの足し算を学習した後、ジャンプの学びで□+□=7のような問題に取り組むようなイメージです。□の中にいろいろな数字を入れながら確かめることで、学力が高い子は、法則に気付き、学力の低い子も、何度も足し算の処理をすることで自然と足し算の仕方は定着するということです。
意外かもしれませんが、学力が低い子ほどジャンプの課題に夢中になるそうです。お互いに協力し、支え合い、探求し合う形をつくることで、できる子とできない子が対等に学び合うことができるのだそうです!
真正の学び
文学には文学らしい読みがあり、数学では問題が解けるというだけではなく、問題を解く過程が数学的思考になることと。理科なら、仮説を立てて検証・実験するだけではなく、そこで見えた事象を細かく観察して、説明する。
それぞれの教科において、そこまですることで「探求」になります。
つまり、その教科の背後にある学問や文化の本質に迫るような学びをつくるのが「真正の学び」なのです。各教科の「見方・考え方を働かせる」学びをつくるといってもいいかもしれません。
聴き合う関係をつくり、ジャンプの学びによって基礎の定着を図るとともに、教科の本質に迫っていくような真正の学びをつくっていく。このような一連の探求の在り方が「学びの共同体」なのです。
最後に
正直、学びの共同体のことがうまく伝えられた自信はありません(笑)
しかし、これまで話したように、学びの共同体の公開授業に参加したことで、私の考え方は大きく変わりました。本の中では、たくさんの学校で学びの共同体実践が行われていること、いきいきと学ぶ子供たちの姿や熱心な先生たちの姿が描かれています。
それを読むだけでも私はとても刺激になりました。
もし興味を持った方がいれば、ぜひ読んでみてください。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
|
|
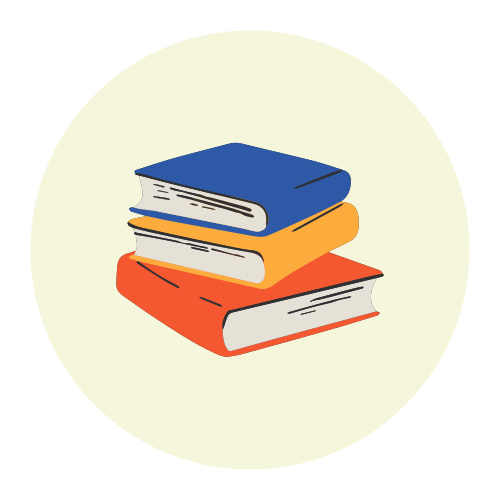
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ffe240e.296cb271.3ffe240f.1c95c8fe/?me_id=1213310&item_id=19177636&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1949%2F9784098401949.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す