こんにちは、ムッタ先生です。
最近は、NetFlixの「あいの里シーズン2」にはまっています!
今回の内容は、ずばりタイトルの通りです!(笑)
授業をしていて、子供たちは同じことを学んでいる。一生懸命にやっている子の学力がなかなか上がらない。地頭の問題なのか?
そんなことを考えたことはありませんか?
先日、本屋さんで発見したこの本!目についた瞬間、即買い!
タイトルは「同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?」著:石田勝紀
買って一気読みしました。今まで疑問に思っていたことへの一つの答えだと思いました。
この本の内容と私が印象に残ったところを紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。
「同じ勉強をしていて、なぜ差がつくのか?」について
著者
石田勝紀さんは、日本の教育専門家であり、教育デザインラボの代表理事です。1968年に横浜で生まれ、20歳で学習塾「緑進学院」を創業し、これまでに4000人以上の生徒に直接指導し、講演会やセミナーを通じて5万人以上の人々に教育の重要性を伝えています。
石田さんは、子育てや教育に関する多くの書籍を執筆しており、「Mama Café」シリーズなどの活動を通じて、親や教育者に向けた情報提供を行っています。彼の著書には「子どもを育てる7つの原則」や「中学生の勉強法」などがあり、多くの家庭で参考にされています。
内容
この本では、同じ環境で同じ勉強をしているのに、なぜ成績に差が出るのかについて探求しています。石田さんは、できる子とそうでない子の違いを「本質的な理由」に基づいて説明しています。
親や教育者が子どもたちの学習をサポートするための実践的なアドバイスがたくさん紹介されています。
印象的な内容
「学び」には3つのタイプがある?
本書は、同じように勉強しているのにどうして差が出るのか、その理由を探る内容となっています。教師であれば、日々子どもたちの姿を見て、その現実を実感していることでしょう。
著者は、「学び」には大きく分けて次の3つのタイプがあると述べています。
- 授業を受けていても学んでいない人
- 授業だけが学びの人
- 寝ているとき以外、日常すべてが学びの人
あなたのクラスの子どもたちを思い浮かべてみてください。
- 1のタイプ
授業に集中せず、考えを発表することもノートに書くこともない子。友達の意見や黒板の内容を写すだけの受け身な態度が目立つでしょう。 - 2のタイプ
授業中は先生の話に集中し、発表やノートを熱心に取り組む子。しかし、家庭学習や自主学習では必要最低限しか行わない。多くの子がこのタイプに当てはまるかもしれません。 - 3のタイプ
授業中、友達や教師の発言に疑問をもち、積極的に発言する子。家庭学習では興味のあるテーマを深掘りし、さらに難しい課題にも挑戦する姿が見られるでしょう。いつでもどこでも学んでいる状態です。
私の経験でも、圧倒的に多いのは1や2のタイプの子どもたちです。特に2のタイプで、授業に一生懸命取り組んでいるのに学習が定着しない子を見ると、教師としてどうしたらよいものか、もどかしさを感じます。
「意味」を理解しているか?
保護者との会話で「うちの子、国語が苦手なんです。本を読ませてるんですけど」という相談を何度も受けたことがあります。読書をすることで国語力が上がるのか――私自身、かつては答えに困っていました。
確かに、読書はしないよりしたほうがいい。実際、本をよく読む子のほうが学力が高い傾向があると感じています。しかし、本を読んでいるのに国語が得意な子と苦手な子がいるのはなぜでしょうか?
著者は、文章の読み方には次の2種類があると指摘しています。
- 意味を理解しながら読む読み方
- 字ヅラだけを追う読み方
2の読み方をしている子は、国語が苦手なだけでなく、他教科にも影響が出るといいます。
どちらの読み方をしているかは外からは分かりません。ただ、本を「読む」だけでは、字ヅラを追っているに過ぎないこともあります。意味を理解しながら読むためには「考える力」が必要です。
例えば、算数の文章問題が苦手な子を思い浮かべてみてください。意味を理解して読んでいる子は、問題文から具体的なイメージを思い浮かべ、「そんな状況、あるのかな?」と疑問を持つこともあります。これは、文章の内容を理解しているからこそできる反応です。
一方、字ヅラを追っているだけの子は、出てきた数字をそのまま式に並べて計算するだけで、なぜその式になるのか説明できません。この違いは「考えながら読んでいるかどうか」に起因します。
考える力を育てる2つのアプローチ
では、どうすれば考える力を育てられるのでしょうか? 著者は次の2つのアプローチを挙げています。
1.疑問を持たせる
子どもたちは幼いころ、何にでも「なんで?」と疑問をぶつけていたはずです。しかし、成長とともに疑問を抱く機会が減り、興味関心のある分野だけに意識が向きがちです。
意識的に「なぜだろう?」と問いかけることで、子どもの思考が動き出します。この習慣を繰り返すことで、考える力が高まります。
2.まとめさせる
「まとめる」とは、具体的な内容を抽象化したり、逆に抽象的な内容を具体化したりする力を指します。これは考える力を持つ人の特徴でもあります。
例えば、子どもに「要するにどういうこと?」「例えばどういうこと?」と問いかけることで、抽象的な思考や具体的な理解を促すことができます。このプロセスを繰り返すことで、考える力が磨かれます。
どちらのアプローチも子供の思考を促し、考える力を育むためのアプローチです。大切なのは、これらの問いかけにより、考えることを習慣化していくことなのです。
まとめ
同じ勉強をしているのに、なぜ差がつくのか。その答えは考える力の差にありました。日々の授業の中で、いかに考える力を育むことができているでしょうか?
授業中、子どもたちに問いかける場面は多くあります。本書では、その問いかけをより効果的にするための「考える力を育てるマジックワード」が10個紹介されています。これを読んでから、私自身も問いかけの言葉を意識するようになりました。
この本に興味を持った方は、ぜひ手に取ってみてください。きっと新たな発見があるはずです。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
|
|
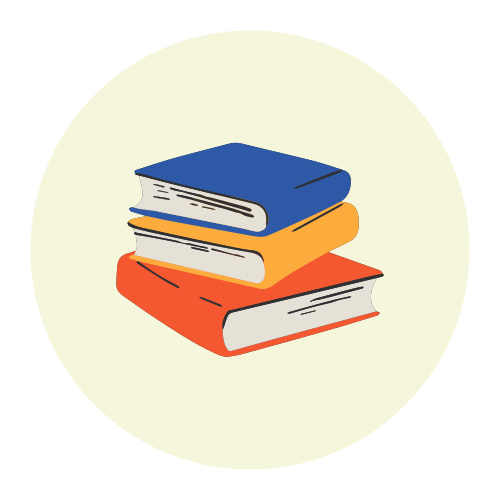

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/40b96bc3.0fa8ce8e.40b96bc4.e760f7f0/?me_id=1276609&item_id=13241107&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01229%2Fbk4799330861.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す