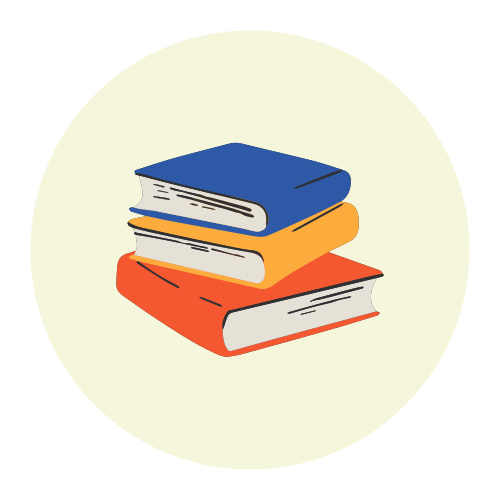こんにちは、ムッタ先生です!
「例年通り」「昨年と同じように」
こんな言葉、よく耳にしませんか?
私の学校では、会議のたびに3回は出てきます。
教師としての経験を積み、本を通じて学びを深める中で、「例年思考」や「変わらない・変えたくない」という意識が、学校のアップデートを阻む一因だと感じるようになりました。
いくつかの具体例を挙げながら話していきたいと思います。
持久走大会の例
例えば持久走。私の学校では昨年まで、全員が記録を取り、上位8人を表彰する持久走大会を行っていました。
私自身、小学生の頃、足が遅くて持久走が大嫌いでした。多くの保護者や参観者の前で走るのも苦痛だった記憶があります。
教師になってから気づいたのは、当日欠席や練習を体調不良で見学する児童が少なくないことです。持久力を高めるはずの教育活動が、大会という形に縛られ、本来の目的を損なっていると感じました。そのため、方法を変えるよう訴えてきました。
しかし、同僚たちからは
- 「保護者が見たいと言っている」
- 「持久走で一位になる子の輝く場を奪えない」
- 「新しいやり方を考えるのは大変」
など、変えないための理由ばかり挙がります。すべてを否定したいわけではありませんが、果たしてこれで子供たちにとって本当に良いのでしょうか?
ICT教育の例
また、ICT教育も似た状況です。普及が進む一方、全く活用していない教師もいます。
理由を尋ねると、「使い方が分からない」「別にタブレットがなくても授業はできる」という声が返ってきます。しかし、これからの時代を生きる子供たちには、ICT機器の活用は必要な学びの一つです。使い方を覚えるのが大変、という理由で変わらない姿勢は、子供たちのためになりません。
変わるべき理由
私たち教師の仕事は、クビになる心配もなく、給料にも大きく影響しないため、苦労して変わろうとしなくても成り立ってしまう側面があります。
ですが、目の前の子供たちが将来の日本を支える存在になることを考えれば、私たち自身がアップデートし続けるべきです。
これについては、先日の記事【雑談】教師は社会を知らない?-Nontitleから考える-でも触れましたので、合わせてお読みいただけると嬉しいです。
もちろん、教師の労働環境を改善し、勉強の時間を確保することも重要です。文科省や教育委員会がその支援に積極的になるべきだと思います。
「淀む水に芥たまる」
静止した水には汚れがたまるものです。この言葉は、変化しない日常や仕事も同じだという教訓を示しています。組織としても、個人としても、改善や挑戦を続けることが大切です。
昔、NHKの『プロフェッショナル』で、ある医師が「自分が成長できなくなった時が辞め時だ」と言っていました。その言葉を思い出し、常に成長を続ける教師でありたいと改めて感じています。
この記事を、戒めのためにも記録として残しておきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!